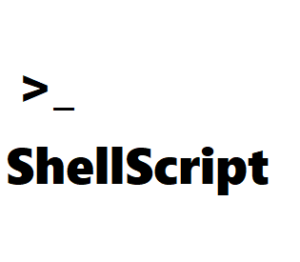シェルスクリプト
シェルスクリプト while文(2)
while文の条件ですが、進捗をみるときに消去していない(=消去完了しているとき)は以下のように Not In Progressと出るのでNotの有無で完了/未完了を判別したいと思います。これにはgrepを用いて とすれ […]
シェルスクリプト while文(1)
話が前後して申し訳ないですが、storcliコマンドで消去の進捗を見るには、 で可能です。ただこれだとコマンドの実行時点での進捗率しか見ることができません。そんなときはコマンドを一定時間ごとに実行する watch コマン […]
シェルスクリプトで関数の定義
シェルスクリプトで関数を定義するのは簡単で、 のように記述すればよい。 たとえば、単にターミナルに「This is the Function.」と表示させるだけなら関数名をfuncとすると とすればよく、以下のようにスク […]
SAS HDDのSMART情報を取得(3)
前回、認識されているSAS HDDを以下のように表示させました。 次に、[ /dev/bus/0 -d megaraid,2 ]のSMART情報を表示させます。コマンドを以下のように実行すると表示させることができます。 […]
SAS HDDのSMART情報を取得(2)
CentOS7をインストールしたところで、smartmontoolsというアプリケーションをインストールします。通常、CentOS7には明示的にインストールしなくても、パッケージとして一緒にインストールされますが、もし導 […]
SAS HDDのSMART情報を取得(1)
HDDにはSMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)情報というものが備わっていて、そのHDDのいろいろな情報を得ることができます。たとえば、通電時間 […]
シェルスクリプトでディスク消去(8)
HDDを消去したあと、その中身について実際にランダムな文字列であったり、ゼロであったりで全体が上書きされているか確認したいところです。その確認にはhexdumpというコマンドで実現できます。 hexdumpのヘルプを見る […]
シェルスクリプトでディスク消去(7)
さて、消去したあとでなんとなくログに吐き出して保存しておきたくなると思います。そこで、ハードウェア情報と消去方式とHDDのダンプの一部を出力してそれをシリアルナンバーのファイル名で保存しようと思います。 まずはこれを実現 […]
シェルスクリプトでディスク消去(6)
消去方式を選択した後は、その方式に応じて処理を分岐させる必要があります。分岐処理ではif文を使うのが普通ですが、分岐先が4つあるのでコードが複雑になってしまいます。そこで、もう1つの分岐処理であるcase文を使用します。 […]
シェルスクリプトでディスク消去(5)
さて、消去処理ですがただ消去実行だけでは面白くないので、さらに処理を分岐させます。 shredコマンドでは色々なオプションが用意されています。--helpオプションをつけて実行します。 消去方式として、①乱数を発生させ意 […]